肩こりにお悩みの方は多いことでしょう。
肩こりには様々な原因がありますが、筋肉が関係していることが多いです。
では肩こりに関係のある筋肉はどこなのでしょうか。
原因となる筋肉に適切にアプローチすることで、肩こりが軽減されるでしょう。
ここでは、僧帽筋などの筋肉と肩こりの対処法をご紹介します。
□肩こりに関係する筋肉とは
そもそも肩こりとは、首の後ろや背中にかけて不快な状態に陥る症状の総称です。
首や肩の関節は動きの幅が大きく、その分常に緊張している状態になります。
この緊張が続きすぎたり、変な圧力がかかったりすると肩こりにつながります。
ここではそんな肩こりに関係している筋肉をご紹介します。
1つ目は僧帽筋(そうぼうきん)です。
これは首から背中にかけて広がっている筋肉で、肩こりに最も大きな影響がある筋肉だと言われています。
特に首をすぼめたときに痛みが生じる場合は、僧帽筋に問題があることを疑っても良いでしょう。
2つ目は肩甲挙筋(けんこうきょきん)です。
これは首と肩甲骨をつなげる筋肉です。
この筋肉も僧帽筋と同様な働きをしています。
3つ目は頭板状筋(とうばんじょうきん)です。
これは首の後ろ側にある筋肉で、首を伸ばすときに使う筋肉です。
この筋肉が凝り固まっていると、首をうまく後ろに曲げにくくなるでしょう。
□筋肉からくる肩こりの対処法とは
このように僧帽筋をはじめとする多くの筋肉が肩こりと関係していると言えるでしょう。
ここでは筋肉からくる肩こりの対処法をご紹介します。
1つ目はストレッチをすることです。
毎日ストレッチをすることで、緊張状態にある筋肉を適度にほぐせるでしょう。
特に朝は身体が凝り固まっていることが多いので、朝一番にストレッチをすると気持ちよく1日を始められるでしょう。
2つ目はつぼを押すことです。
首や肩の周りには、肩こりに効果的なつぼが集まっています。
適切なつぼを押すことで、肩こりの改善につなげやすいでしょう。
つぼを刺激する際には、痛めすぎないように力加減には気を付けることをおすすめします。
3つ目は温めることです。
肩こりは僧帽筋などの筋肉の血行が悪くなることで起こります。
そのため、血行を良くするために肩をお風呂や蒸しタオルで温めると良いでしょう。
温めた状態でつぼを押したりストレッチしたりすることも効果的です。
□まとめ
今回は僧帽筋などの筋肉からくる肩こりと、その対処法についてご紹介しました。
肩こりが筋肉と深い関係にあることが理解していただけたのではないでしょうか。
今回の記事を参考にして、肩こりの改善をしてみてください。
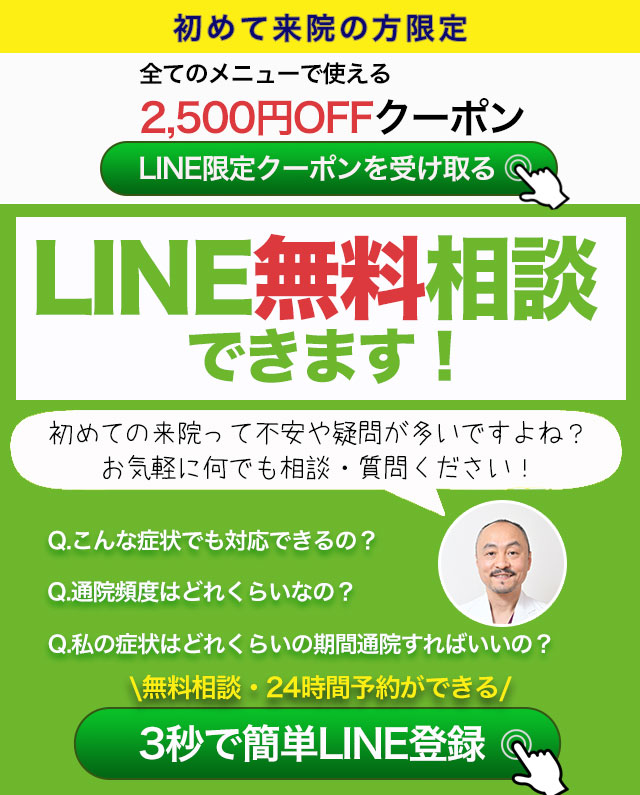

電話でのお問い合わせ・ご予約は
- 大学院(生命工学)を修了、大学院時代は国立予防衛生研究所(現、国立感染症研究所)にて研究を行う
- 大学院を修了後、食品会社にて研究および衛生管理に携わる。その後、鍼灸専門学校に入学、鍼灸師、鍼灸専門学校講師となる。
- 東京衛生専門学校東洋医療総合学科、及び、同校臨床教育専攻科(教員養成課程)卒業。
- 牧田総合病院附属、牧田中医クリニックにて5年間研修をおこなう。
- 同クリニックにて脳血管障害に対する鍼灸施術法、醒脳開竅法(せいのうかいきょうほう)上級の課程を修了。
- 山元リハビリクリニックにてYMSA短期研修を受ける。
- 鍼灸専門学校の非常勤講師として鍼灸の指導を行いながら、施術院にて鍼灸・マッサージ施術の多数の臨床経験を積む。

 お問い合わせ
お問い合わせ 0270-75-3443
0270-75-3443



 きよ治療院の交通事故治療では、交通事故に生じてしまった怪我(ムチウチ等)を集中的に通って頂き治療を行います。鍼で直接アプローチすることで、痛みや緊張、神経圧迫の緩和などを目指します。
きよ治療院の交通事故治療では、交通事故に生じてしまった怪我(ムチウチ等)を集中的に通って頂き治療を行います。鍼で直接アプローチすることで、痛みや緊張、神経圧迫の緩和などを目指します。
 「きよ治療院」独自の施術法です。脳を活性化し、促通を行います。通常のリハビリと併せて鍼灸を取り入れることで、運動機能の回復・自律神経の調整効果などが期待できます。
「きよ治療院」独自の施術法です。脳を活性化し、促通を行います。通常のリハビリと併せて鍼灸を取り入れることで、運動機能の回復・自律神経の調整効果などが期待できます。
 日本ではあまり知られていませんが、世界でもっとも医師が実践している鍼施術の1つです。YNSAでは、脳を活性化させることで、各症状の改善を促します。 特に脳脊髄神経や脳血流、脳脊髄液の巡りを高める効果があるため、神経系の問題や慢性疲労に悩む方におすすめの治療法です。
日本ではあまり知られていませんが、世界でもっとも医師が実践している鍼施術の1つです。YNSAでは、脳を活性化させることで、各症状の改善を促します。 特に脳脊髄神経や脳血流、脳脊髄液の巡りを高める効果があるため、神経系の問題や慢性疲労に悩む方におすすめの治療法です。
 鍼灸治療は、血流の改善や筋肉の緊張緩和、自律神経の調整に効果が期待できます。また、痛みの軽減や睡眠の質向上にも役立つため、慢性的な腰痛や膝の痛み、不眠症、倦怠感など、高齢者特有の症状に適しています。
鍼灸治療は、血流の改善や筋肉の緊張緩和、自律神経の調整に効果が期待できます。また、痛みの軽減や睡眠の質向上にも役立つため、慢性的な腰痛や膝の痛み、不眠症、倦怠感など、高齢者特有の症状に適しています。
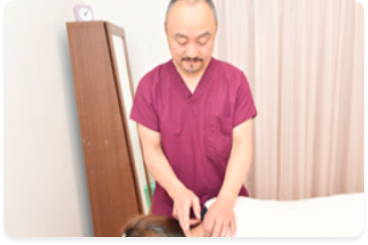 鍼灸治療は、血流を改善し、自律神経を整えることで、妊娠しやすい身体作りをサポートします。また、妊活中のストレスや不安感を和らげるためのリラクゼーション効果も得られるため、心身のバランスを整えるのに役立ちます。
鍼灸治療は、血流を改善し、自律神経を整えることで、妊娠しやすい身体作りをサポートします。また、妊活中のストレスや不安感を和らげるためのリラクゼーション効果も得られるため、心身のバランスを整えるのに役立ちます。
 鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和し、血流を促進することで、疲労回復や柔軟性が向上します。さらに、痛みを和らげる効果が期待できるため、筋肉痛、捻挫、肉離れといったケガの治療にも効果的です。また、自律神経を整えることで集中力やリカバリー力を高める効果もあります。
鍼灸治療は、筋肉の緊張を緩和し、血流を促進することで、疲労回復や柔軟性が向上します。さらに、痛みを和らげる効果が期待できるため、筋肉痛、捻挫、肉離れといったケガの治療にも効果的です。また、自律神経を整えることで集中力やリカバリー力を高める効果もあります。
 美容鍼灸は、自然な方法で美しさを引き出す鍼灸治療です。きよ治療院では、顔や体の内側にアプローチし、肌のトラブル改善やアンチエイジングをサポートしています。
美容鍼灸は、自然な方法で美しさを引き出す鍼灸治療です。きよ治療院では、顔や体の内側にアプローチし、肌のトラブル改善やアンチエイジングをサポートしています。
 長時間のデスクワークやパソコン作業が続くと、肩こりや腰痛、目の疲れ、頭痛など、身体や心にさまざまな不調を引き起こすことがあります。デスクワーカーの皆様が抱えるこれらの悩みに特化した鍼灸治療を提供し、仕事の効率を上げるサポートをいたします。
長時間のデスクワークやパソコン作業が続くと、肩こりや腰痛、目の疲れ、頭痛など、身体や心にさまざまな不調を引き起こすことがあります。デスクワーカーの皆様が抱えるこれらの悩みに特化した鍼灸治療を提供し、仕事の効率を上げるサポートをいたします。
 過酷な労働や長時間の勤務が続くと、身体に大きな負担がかかり、疲れや痛みが蓄積していきます。ハードワーカーの皆様が抱える慢性的な疲労や筋肉の痛み、ストレスなどに対し、効果的な鍼灸治療を提供し、心身のリフレッシュと回復をサポートします。
過酷な労働や長時間の勤務が続くと、身体に大きな負担がかかり、疲れや痛みが蓄積していきます。ハードワーカーの皆様が抱える慢性的な疲労や筋肉の痛み、ストレスなどに対し、効果的な鍼灸治療を提供し、心身のリフレッシュと回復をサポートします。

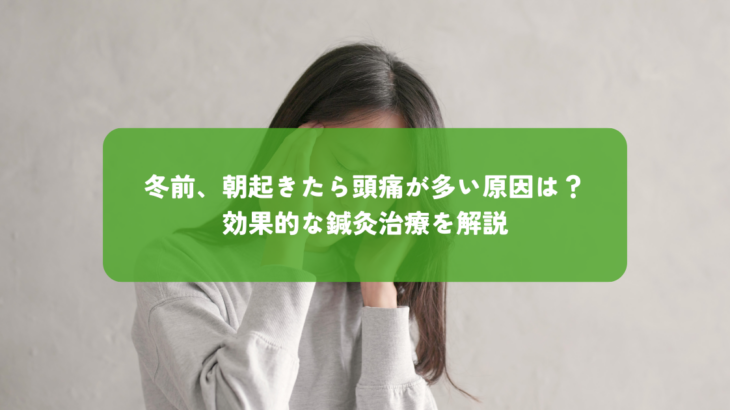
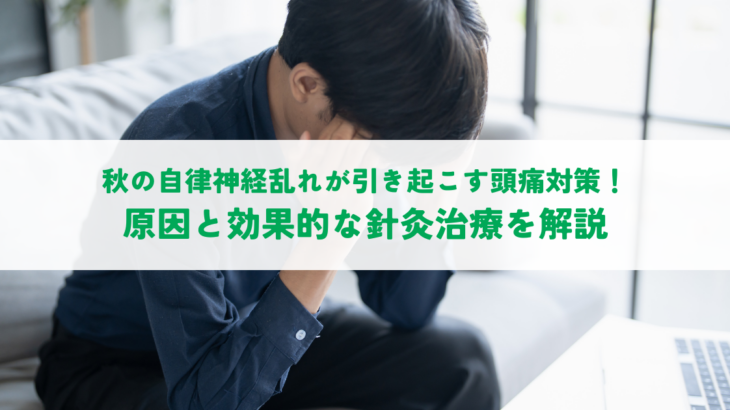
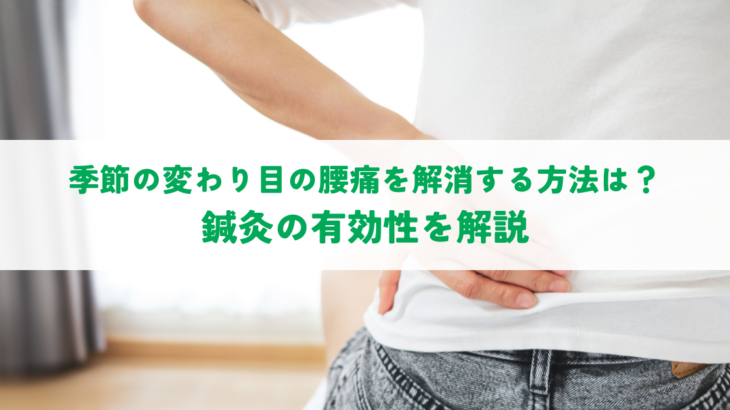
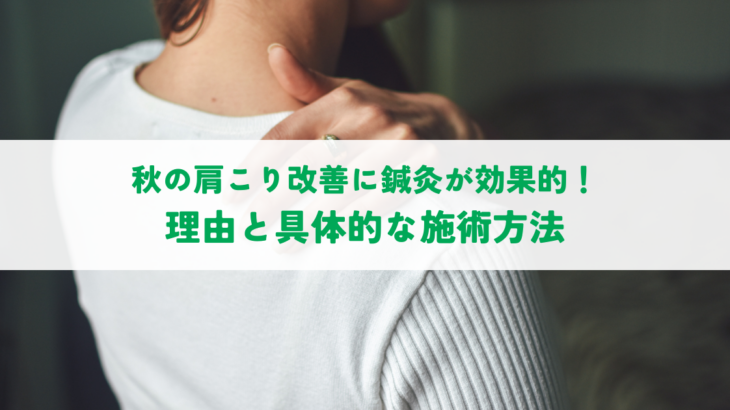
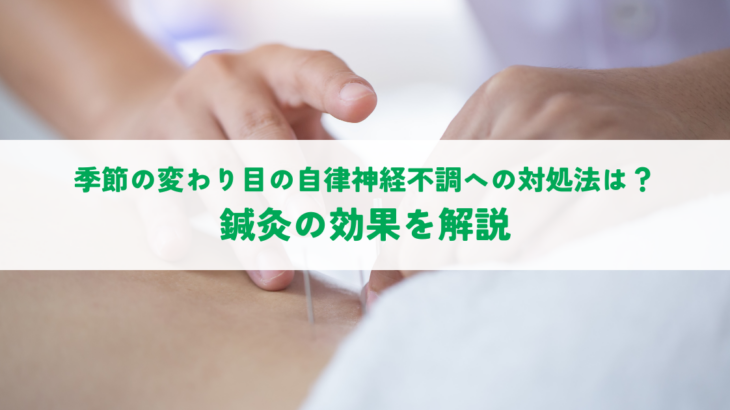

 お問い合わせ
お問い合わせ お電話
お電話